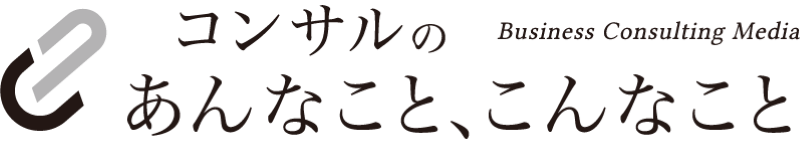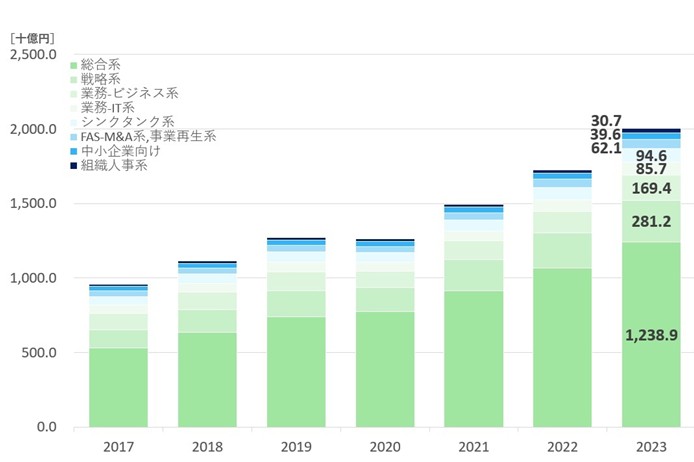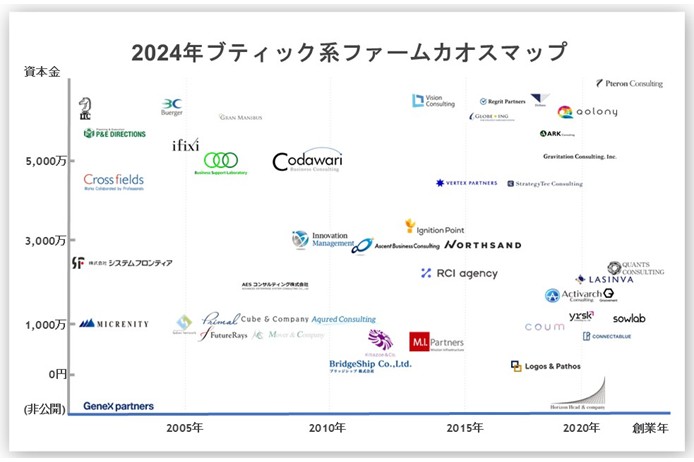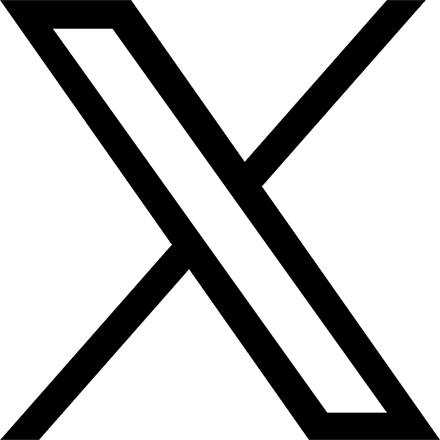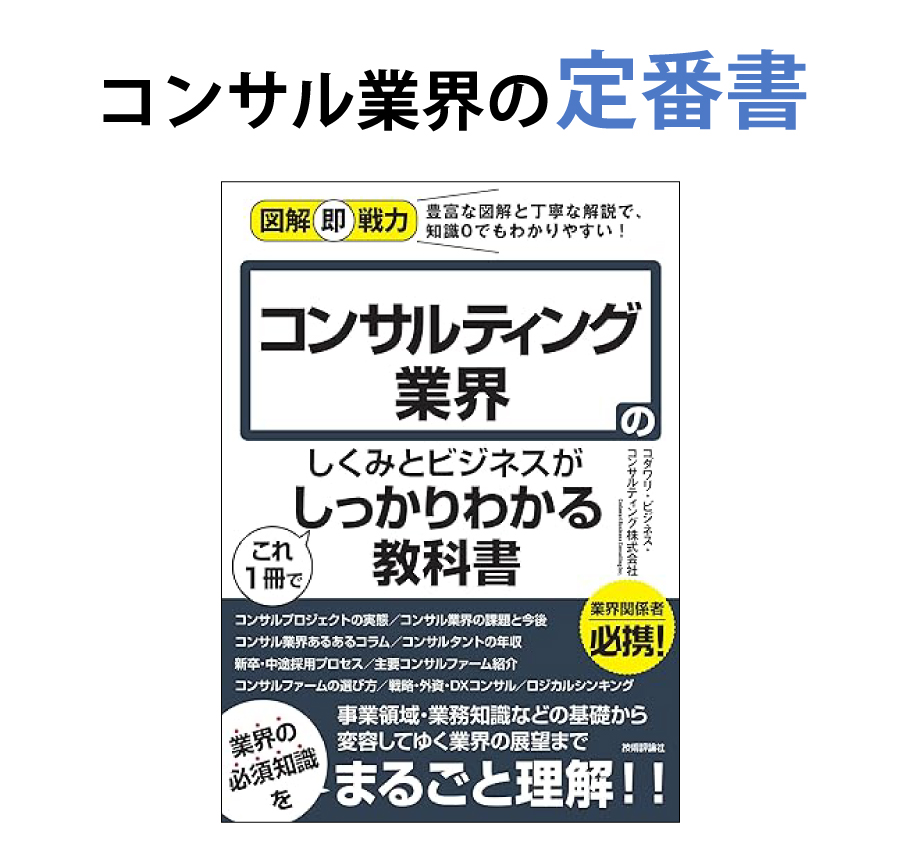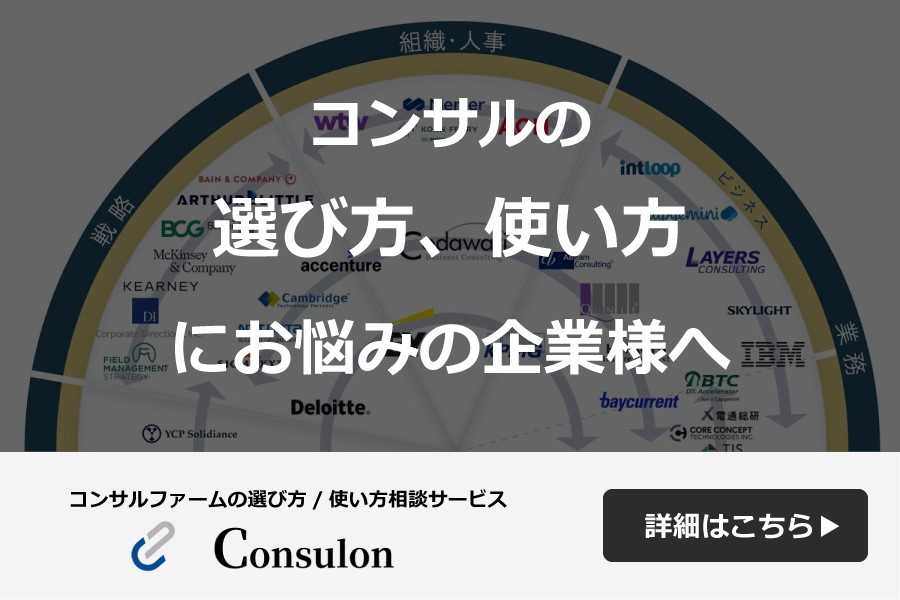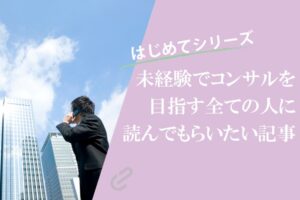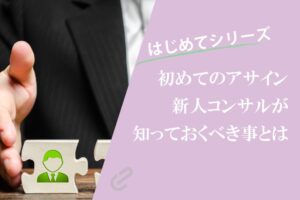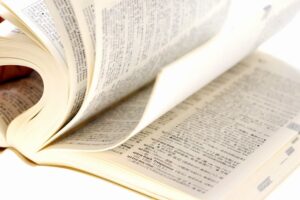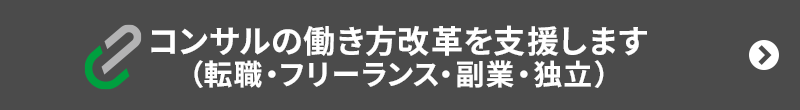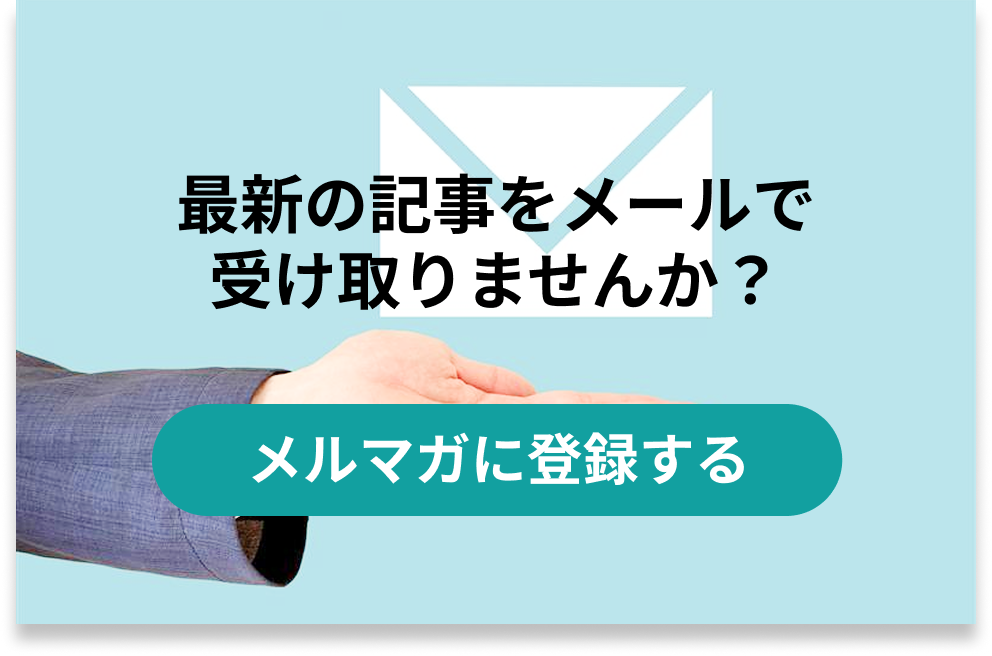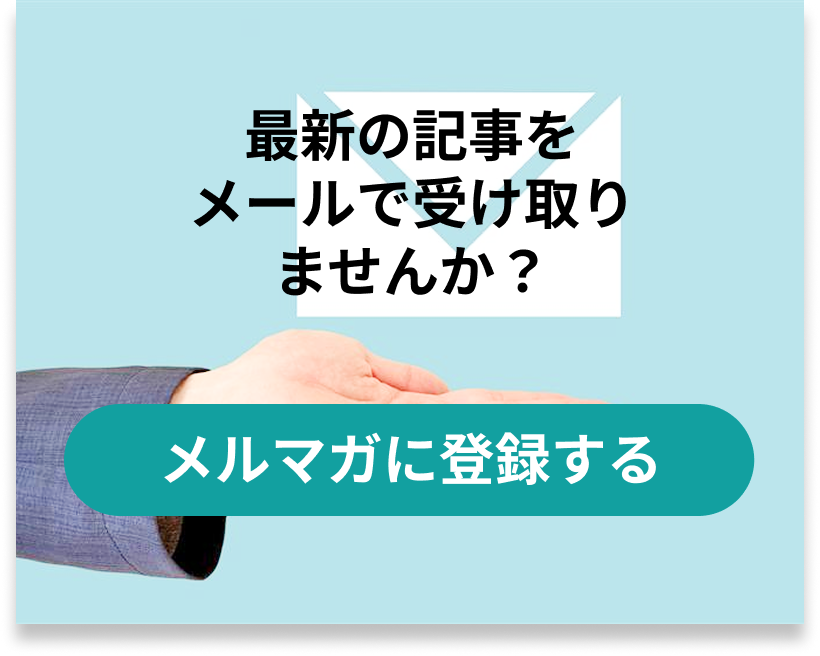view 7628
NHKと日本IBMの訴訟を身勝手にITコンサルが紐解いてみた | コンサルのホンネ

ITシステムプロジェクト訴訟報道(NHK vs 日本IBM)に寄せるコンサルの想い
現役コンサルが徒然なるままに綴るコラム「コンサルのホンネ」では、ハードワークの合間に思いついたことを思いつくままに語ります。 第13回のテーマは「NHKと日本IBMの訴訟を身勝手にITコンサルが紐解いてみた」。ホッと一息つくも良し、同じテーマで考察してみるも良し、お気軽にお読みください。
様々なメディアで報道されている通り、NHKが日本IBMに対してシステム構築・移行費用の損賠賠償と支払済み金額の返還を求めて民事訴訟を起こしました。
大規模なITシステム刷新プロジェクトの前フェーズを幾度となく経験し、山あり谷ありを乗越えてきた(生きながらえた)現役コンサルタントの訴訟発表へのホンネです。
目次
訴訟の概要
両社発表
◆[NHK]報道資料 2025年2月4日 システム開発中止に伴う訴訟の提起について
◆[IBM Japan]Newsroom – 2025年2月7日 NHKシステム開発・移行中断の件について
訴訟額
◆請求総額:54億6992万円(既払い金31億円+損害賠償23億6992万円)
対象システム
◆(受信料関連の業務全般を担う)営業基幹システムで、現行システムは富士通メインフレームで稼働中
両社の主張
◆NHK側:日本IBMの進捗管理不備が遅延原因
◆日本IBM側:複雑なレガシーシステムの構造が想定外で、リスクを適切に報告
訴訟に至るまでの経緯
◆2022年12月:27年3月を納期とする新システム開発の業務委託契約を日本IBMとNHK間で締結(約80億円)
◆2024年3月:日本IBMが「開発方式の大幅見直し」を通告、5月には納期が18ヶ月遅延する可能性を報告
◆2024年8月:NHKは、現行システムの耐用期限切れによる業務影響を懸念して日本IBMとの契約を解除
両社の主張
発表文書を確認すると、両社の主張にはどちらがルールを決めたかという責任の押し付け合い感が漂います。そのほか「開発方式」、「移行方針」と出てくるように、プロジェクトフェーズにズレがありそうで、どこの何が悪かった、それは誰の責任かが争点になるのは目に見えてます。
NHK発表資料(抜粋)
「日本IBM社は、新システムの開発方式を定め、1年2カ月以上業務を進めてきましたが、2024年3月に入って突然、大幅な開発方式の見直しが必要であると述べ、その後、2024年5月には、納期について1年6カ月以上もの大幅な延伸が必要との申し入れがありました。」
日本IBM発表資料(抜粋)
「NHK指定の移行方針のもと営業基幹システムを新しい基盤へ移行するものであり、プロジェクト開始後に現行システムの解析を実施の上、移行方針及びスケジュール等を確定するという契約に沿って検討を進めてまいりました。」
考えられる争点
法律家でないので的確な表現はできないものの、一業界人としては気になるところです。素人発想ではありますが、(和解含む)白黒はっきりさせるために、下記争点が考えられます。
争点へ向けての前提整理
- 契約形態:どのフェーズをどの範囲でどのような形態で契約することになっていたか(第五章で詳説)
- 責任:各社何をどのような責任範囲で実施することになっていたか
- 成果物:どのフェーズで誰が何をどの状態まで作り上げることになっていたか
想定される争点
- プロジェクトの進め方:どのような方針や計画のもと、システム構築(移行含む)方式が、両社でどのような合意事項であったか(発表文を見る限り、進め方に大きな違いがある)
- 要求の適切性::要求仕様の網羅性、それを踏まえたIBMの要件定義とNHKの要求の妥当性(第四章で詳説)
- 進捗状況:どのフェーズで中断となり、それまでのアウトプット、今後の見通しは適切なのか
- 進捗管理:受注者側IBMの進捗管理は適切であったか、発注者側NHKの管理責任は適切であったか
- 両社のアクション:訴訟に至るまでの両社のアクションは適切だったか(IBM発表文では、IBMは善管注意義務に相当するアクションを起こしたと読みとれる)
- エビデンス:エビデンスベースで双方どこまで主張できるか
補足 ~要求の適切性
システム構築関連の過去訴訟でも、「要求の適切性」は大きな争点の1つとなっています。(例:野村HDと日本IBM、旭川医科大学とNTT東日本)
- 要求の網羅性:NHKが作成したという要求仕様の最適性(漏れが無いか)
- (漏れが無い場合)NHK側の主張は適切であり、なぜ再要件定義をしたかの論議
- (漏れがあった場合)IBMによる要件定義は適切に行われたか、NHK側の要求過多はなかったか
IBMの「現行システムの解析を進める中で、提案時に取得した要求仕様書では把握できない」という主張から現行システム分析・再要件定義が必要になり、開発コストを再算出せざるを得なかったものだと思われます。
大規模システムの再構築は複数サブシステムで構成されたり、(NHK内部、NHK外部問わず)複数の周辺システムに依存したり、既存業務やリリースする頃の新業務にも依拠するので、検討事項は多くなるのは必然です。
その要件をNHK側で取り纏めていたとのことですが、そこに抜け漏れが無いか、適切にIBMへ提供できていたのかが争点になると考えます。
また、IBMはNHK側から提供された要件を適切に理解していたのか、要件漏れや不十分な部分を適切にNHKへエスカレーションしていたのかも争われるでしょう。
補足 ~契約形態
冒頭のとおり、両社間で契約形態について見解が異なると思われる節があります。
- NHK発表文では「新システムの開発・移行業務を委託する業務委託契約」
- IBM発表文では「プロジェクト開始後に現行システムの解析を実施の上、移行方針及びスケジュール等を確定するという契約」
一連のフェーズで準委任と請負を分けていたのか、分けているとしたらどのような内容だったか、プロジェクト期間中のリプラン取り決めがどうなっていたか、といった契約形態に関する争いが予想されます。
80億円という規模ですから、プロジェクト開始から終了(最終成果物の納品)まで全て一括請負で締結したとは考えられません。(開発するシステムはクライアントの要望によって大きく変化するので、開発するシステムの要望を詳細化して決める要件定義と基本設計の前段が必要となり、その要望の取り入れ具合で、システム開発コストと期間が大きく変化する)
経済産業省所管の情報処理推進機構(IPA)でも定めています(*1)が、初回契約時は初期工程の要件定義や基本設計の前段を準委任契約(*2)し、基本設計完了までに正式見積もりを算出し、以後の工程を請負契約(*3)するのが定石です。(ただし、NHKは放送協会で法律上、請負で一括じゃないと契約出来ないとかがあり、やむを得ずIBMが呑んだケースも考えられなくはない)
*1 IPA 情報システム・モデル取引・契約書
*2 準委任契約:実施する工数分の請求ができ、納品や完成義務等はない(昨今異なる形態あり)
*3 請負契約:何をいつまでにつくり、その成果物の完成や納品をする義務がある
以降推察です。
IBM側はいざ設計作業に入ったものの、要件に漏れが多すぎてこのままでは開発してリリースしてもシステムに漏れが生じるリスクが高いため、現行システムの分析と要件定義をやり直す必要があると判断。
IBMからNHKへ要件定義に関する申入れをし、NHK側はこれを承認。
いざIBMが要件定義をやり直し、請負契約としての後続フェーズの詳細見積をしたところ、期間の大幅な延伸を言及せざるを得なかった(IBMとしてはそのような契約の認識なので)。
しかしながら、NHK側は期間延伸を受入れられず、契約打ち切り、訴訟となった、という流れでしょうか。
既払い金31億円
既払い金31億は準委任の結果として払われたものだと思われます。工事進行基準によって払われてる部分もあるかもですが、80憶規模の準委任契約部分(要件定義構成+基本設計一部)が31億程度はちょっと比率的には高く感じるものの、異常値ではないと思われます。
将来のITプロジェクトの糧となれ
どちらに責任があるにせよ、プロジェクトがとん挫した原因が裁判の中で明らかになり、サービス提供側・受益側の両方にとって、将来のITプロジェクトの礎になってほしいものです。
[v302]
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー
- SIer・ITコンサルファームでのキャリアを積む。大規模システム刷新プロジェクトにおける業務要求定義からシステム導入運用まで幅広いフェーズや大企業でのDXにおけるPgMOのリーディングや実務をこなす。業務・IT双方へ精通し、関係者との迅速な関係構築のうえ、両面からの業務改革支援に強みを持つ。
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー
- SIer・ITコンサルファームでのキャリアを積む。大規模システム刷新プロジェクトにおける業務要求定義からシステム導入運用まで幅広いフェーズや大企業でのDXにおけるPgMOのリーディングや実務をこなす。業務・IT双方へ精通し、関係者との迅速な関係構築のうえ、両面からの業務改革支援に強みを持つ。