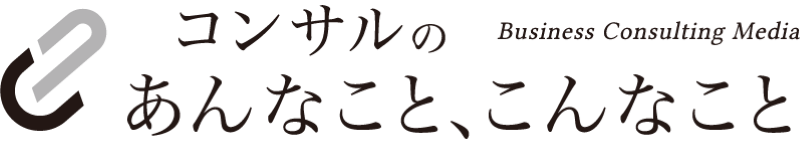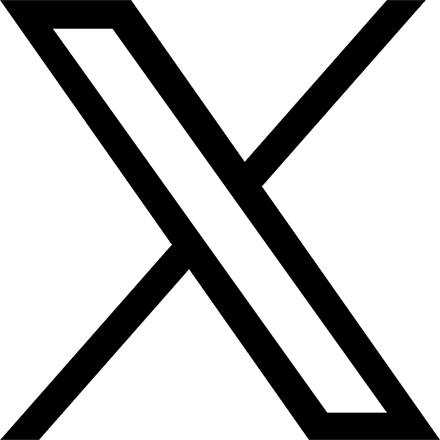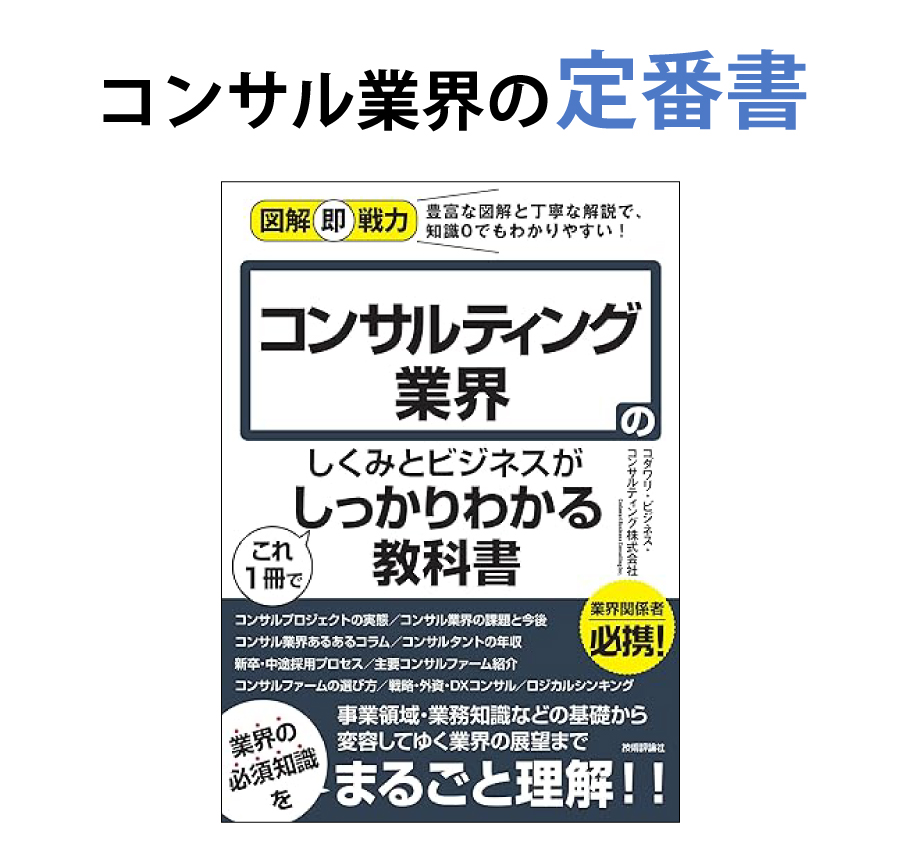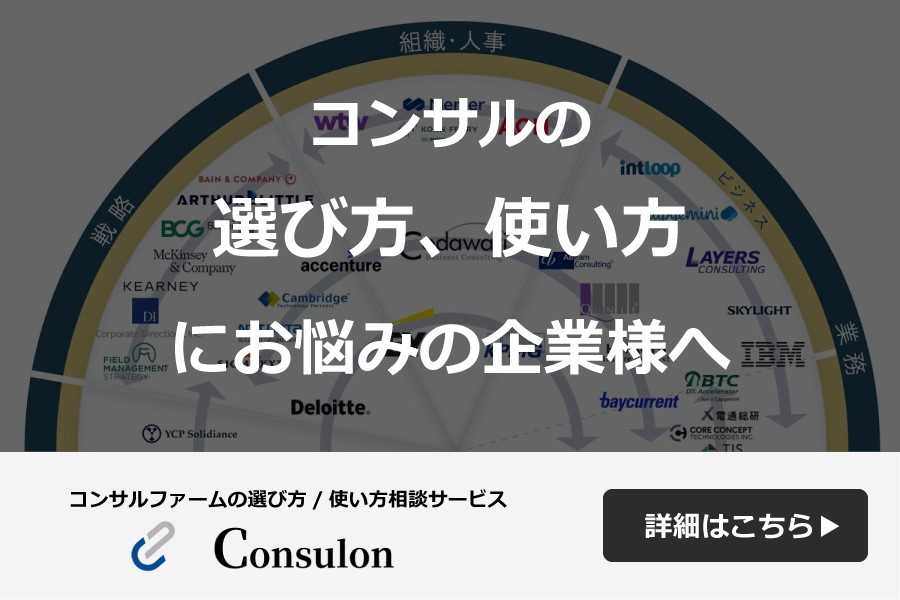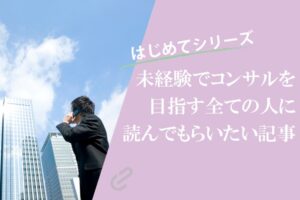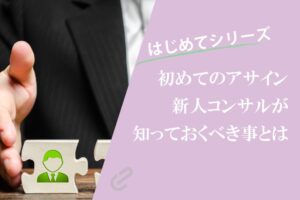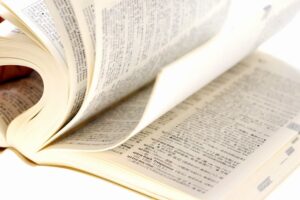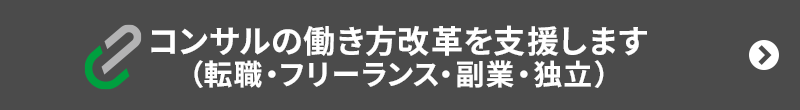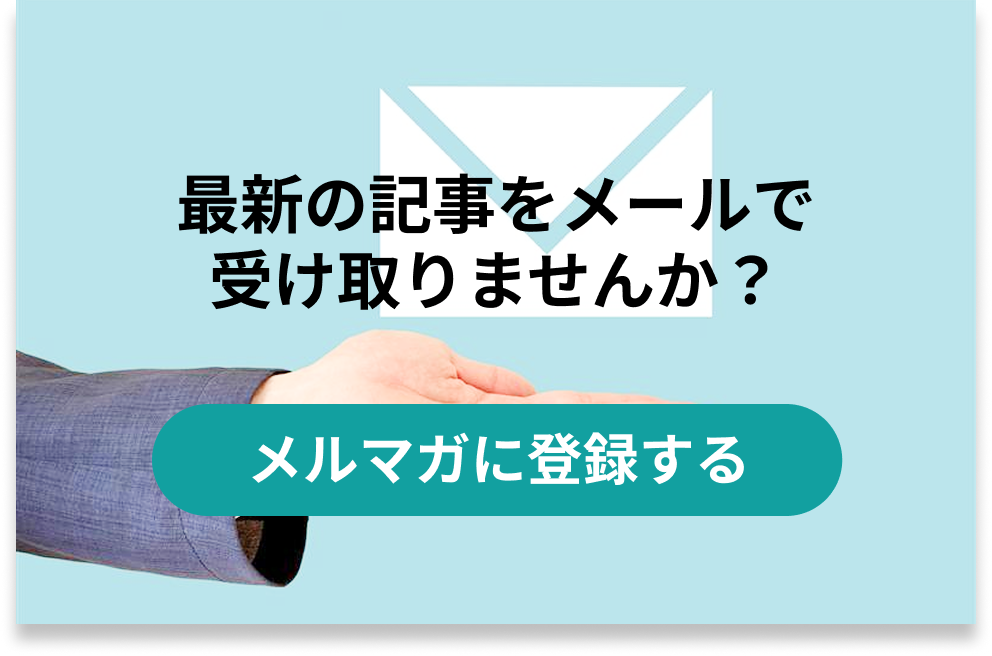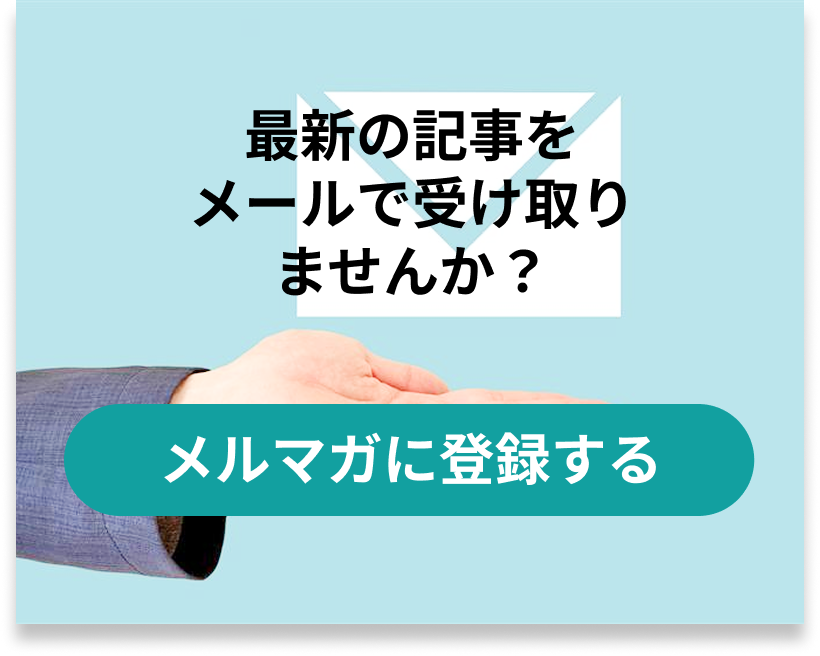view 467
使えないコンサルに悩んだら?~期待外れを“成果”に変える対応法~
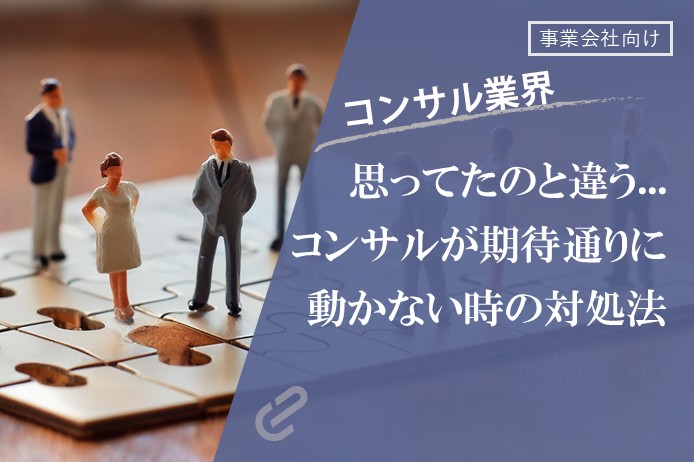
成果を出すためのコンサル活用のポイント
コンサルファームを使っている企業の担当者の中には、コンサルが「イマイチうまく動いてくれない」「思っていたより使えない」とモヤモヤしている方もいるのではないでしょうか。今回、コンサルとスムーズに協業し成果を最大化するにはどうすべきか?を対応法と付き合い方という2つの観点でまとめてみたいと思います。
目次
【そもそも】コンサルに何を期待するのか
そもそもとなりますが、支援を依頼しているプロジェクトにおいて、コンサルに”特に何を期待しているのか”を明確にすると良いと考えます。うまく動いてくれないと感じるのは、期待値とのギャップによるところだと思いますので、期待するポイントを明確にすることで具体的な対応策が取れるようになります。
コンサルには様々な役割/機能がありますが、主に以下8つにまとめることができます。(一部補足しておきます)
・プロフェッショナルアウトソーシング機能
「戦略立案」「業務改善」「IT投資・効率化」「DX推進」といった各専門領域のプロフェッショナルであるコンサルティングファームを使うことにより社内の人材を割くことなく答えを導ける
・ゼロベース思考で客観的にビジネスを効率化する機能
・プロジェクトマネジメント機能
・ファシリテーション機能
プロジェクトを通してコンサルがサポートに回り、クライアント企業の社員が持っている、業界知識や経験をうまく引き出しながら課題解決につなげる
・ベストプラクティス提供機能
コンサルが蓄積した業界・領域の知見を活用し、効果的な課題解決策を提示して実行を支援
・アクションラーニング機能
クライアント社員がコンサルと共に実務を進めることで、実践的な学習と成長が期待できる
・箔付け機能
保守的な風土や社内の反対派を説得するケースなど、コンサルティングファームの権威を借りて意思決定を後押しする
・中立的なアドバイス機能
しがらみのない第三者として、客観的な視点からアドバイスを提供し、意思決定や方針検討を支援
全部を期待しないでくださいとは言いませんが、この中でも期待度が高いのはどれなのかは改めて整理していただくと良いでしょう。
【対応法観点】事前
すでにプロジェクトが走っていて、今さら言われても困るという方もいらっしゃると思いますが、”事前のすり合わせ”がやはり重要です。
主に以下4項目について明確にすることが肝要です。自社側で整理するのが難しい場合は、コンサル側に整理をさせ明確にすると良いです。
・目的(自社としてもっていきたい姿)
・成果目標
・期間・スケジュール、取り組み体制
・業務範囲(支援範囲)
全て大事ですが、中でも業務範囲(支援範囲)について、食い違いがあると取り返しのつかないことになりえます。
新しい取り組みの場合、そもそもクライアント側からすれば困っているからコンサルに依頼をしているわけで、タスクの全体像を把握できておらず、とりあえず何から何までコンサルがやってくれるだろうと思ってしまっても不思議ではありません。
一方で、コンサルファーム側は見積もりや提案書を作成する段階で、プロジェクトの全体像や支援範囲(コンサルとクライアントの業務範囲の明確な線引きも含む)を明らかにし、クライアント側に提示するのが一般的です。ただ、ここの整理が十分ではなく、曖昧さがあるようだと、後々に双方にとって良くないことになります。どこまで何をやってくれるのかが曖昧だと感じたら、より明確化してくれと言ってもいいでしょう。
また、以後のトラブル回避のためには、対象業務範囲を双方で握るだけでなく、契約書に明記しておくことが重要です。ただし、構想フェーズなどプロジェクト開始時点ではプロジェクトの内容が詳細に決まっていないこともありますので、ある程度包括的に明文化するしかないケースもあります。
契約について
コンサルとの契約は1~3か月単位とすることが一般的ですが、この期間で何かしら成果を確認するようにし、延長はするものの成果に満足でないようであれば次の契約で業務範囲をコンサルファーム側と握りなおすと良いです。
【対応法観点】プロジェクト中
ここでは、実際にプロジェクトがスタートしたのに動きが悪いと感じる際の対応法を説明します。特定コンサルタント個人のケースと、関わっているコンサル会社側全体のケースで考えます。
まず、プロジェクトに入っている特定のコンサルタントの動きやパフォーマンスが悪い場合、ストレートに改善してほしい旨や改善されない場合のスイッチをファーム側のアカウント担当(多くの場合ディレクターやシニマネ)に言ってしまうのも対応法の1つです。相性が合わないなどのケースもあると思いますが、相性問題で成果が出ないのであればスイッチを打診してしまって良いと思います。
関わっているコンサル会社側全体のケースだと少々厄介です。早期にアウトプットや成果を出してほしいとプレッシャーをかける、期待役割を改めて伝えるなどの対応が必要になります。
また、コンサルファームが誰かしら(社内の偉い方でも、外部の方でも)の紹介やコネクションきっかけでプロジェクトを受注している場合、そういったつながりのある人に、状況報告や相談をするのは有効です。コンサルファーム側からすると、その人は仕事をつないでくれている大切な存在ですので、信頼を失うわけにはいきません。そのため、状況改善に向けて動かざるを得ないわけです(ある種のエスカレですね)。
そういったやれることをやっても改善が見られない、プロジェクト目標が達成できないと思われる場合は、前項にも書いたように契約を終わらせることを検討しましょう。その上で新たなコンサルファームを選定し、切り替えましょう。
【付き合い方観点】コンサルの間違った使い方
コンサルがダメなケースをある程度念頭においてここまで書いてきましたが、コンサルが動きやすい、つまり成果を出せるような体制やスタンスを取れているか、自社側を振り返ってみることも重要です。筆者はコンサル業界側の立場ですが、だからこそ「コンサルを上手く使ってほしい」との思いからこの点にも触れたいと考えています。
1.コンサルに丸投げする
課題解決の最終判断はコンサルではなくクライアント側がするものです。丸投げして、しかも何をしたいかはっきりしていないのは絶対にNGです。
2.コンサルが解答を知っていると考える
ベストプラクティスはノウハウとして持っているかもしれませんが、事例や1つの型にすぎません。会社や部署、業務によって課題や解決策は変わります。やっといてよ、できるでしょスタンスでは良い結果につながりません。
3.コンサルに嘘をつく(隠す)
正しい情報や現状があってはじめて適切な課題検討が可能です。
【付き合い方観点】コンサルとの関わり方
前項の裏返しになりますが、端的にまとめると以下2点に集約されるかと思います。
1.プロジェクトの「当事者」意識を持つ
コンサルは良い意味であくまで外部の支援者であり、プロジェクトの主役は常にクライアント側になります。
何をしたいのかをはっきりさせることに加えて、コンサルに過度に依存しないようにし、 「コンサルタントに任せれば大丈夫」というスタンスを取らないようにしましょう。コンサルが提供する知見や成果物を、積極的に自社のものとして取込み、今後に活かしていただくことが望ましいです。
さらに、主体的にプロジェクトに関わり、意思決定や課題解決にクライアント側のメンバーが積極的に関与することが重要です。
2.正確な情報と背景を提供する
コンサルが的確な分析や提案を行うためには、クライアント側の持つ情報が命と言っても過言ではありません。
コンサルは外部の立場ですが、プロジェクトにおいては目標達成をするための仲間ですので、オープンな姿勢で情報共有すると良いです。会社の文化、組織構造、過去の経緯、関係者の思惑など、外部からは見えにくい情報をフラットに提供することが重要になります。
また、表面的な要求だけでなく、「なぜその機能が必要なのか」「その業務がなぜ重要なのか」といった背景や目的を共有することも大切です。
つまり、コンサルの使い方の要点としては、解決したいテーマに関して、適切なコミュニケーションを取れる、かつ自社メンバーが主体的に関われる体制を社内整備し、コンサルの知見を有効活用すると同時に、高い生産性を活かしてアウトプット(成果)を早期に量産させ、しっかりと意思決定をしていくこととなります。
「ここまで書いてあることを色々試したけどうまくいかない」
「今使っているコンサルでは成果を出すのは厳しそう…」
そんなお悩みをお持ちの方は、当メディア運営会社 コダワリ・ビジネス・コンサルティング が提供するセカンドオピニオンサービス 『Consulon(コンサロン)』 のご利用をご検討ください。
貴社の状況を丁寧にお伺いし、
・プロジェクトの目的・スコープ・体制・アウトプットは明確か
・コンサルとのコミュニケーションは適切か
などの観点から、客観的なセカンドオピニオンをご提供します。
まずはこちらからお気軽にご相談ください。
[v329]
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルキャリアカンパニー
-
外資自動車メーカー2社を経験した後、コダワリにジョイン。
コンサルティングワークもこなす傍ら、人材紹介事業の事業責任者やコダワリの人材開発業務や採用統括業務など含めて幅広に従事。
最新の投稿
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルキャリアカンパニー
-
外資自動車メーカー2社を経験した後、コダワリにジョイン。
コンサルティングワークもこなす傍ら、人材紹介事業の事業責任者やコダワリの人材開発業務や採用統括業務など含めて幅広に従事。