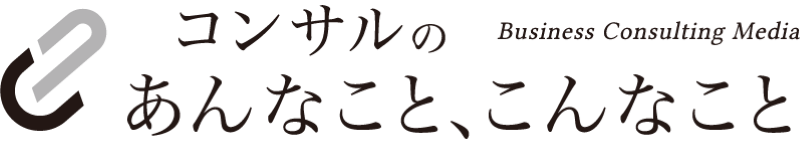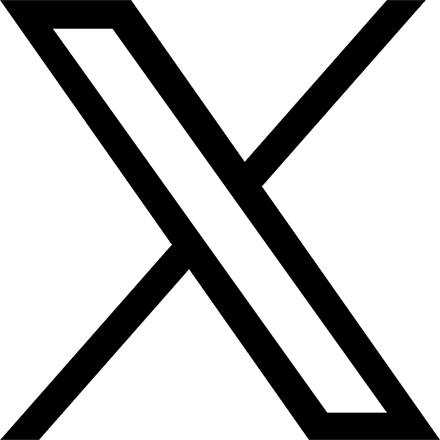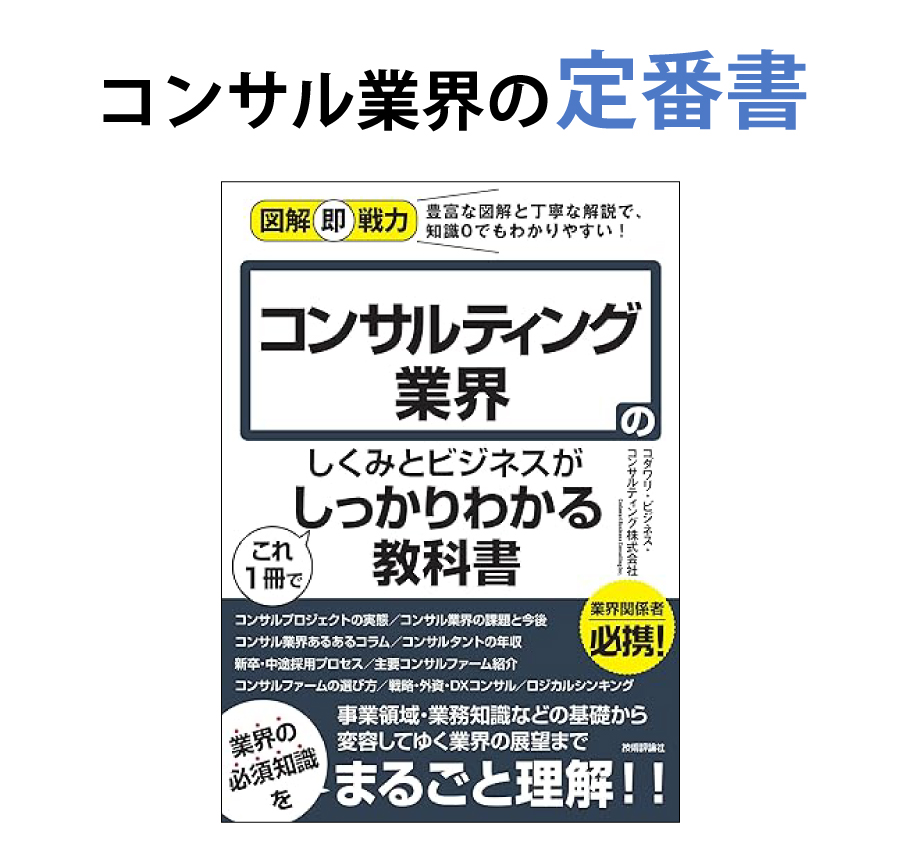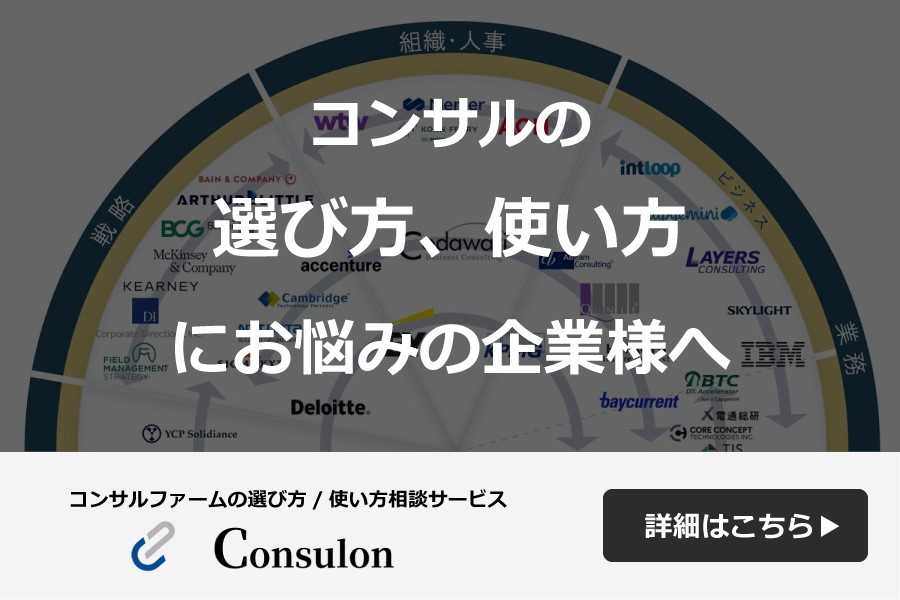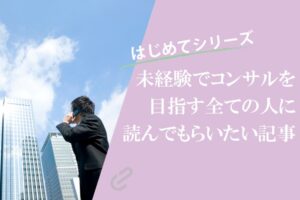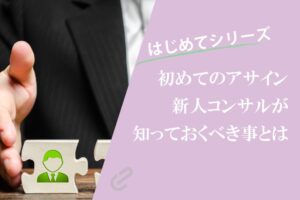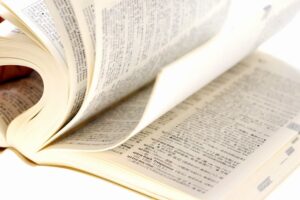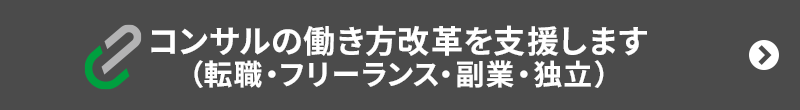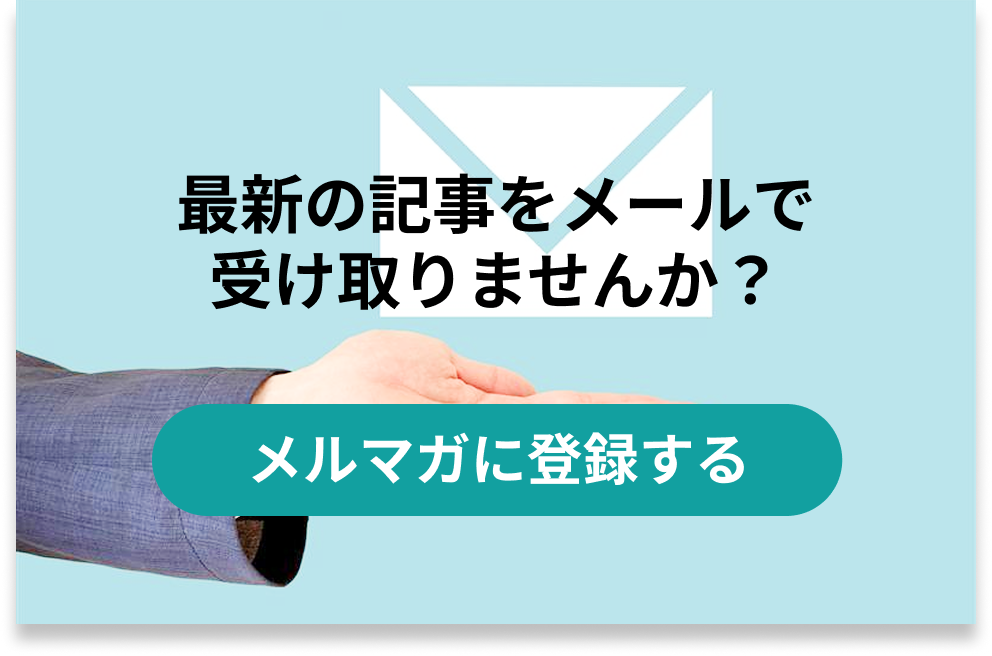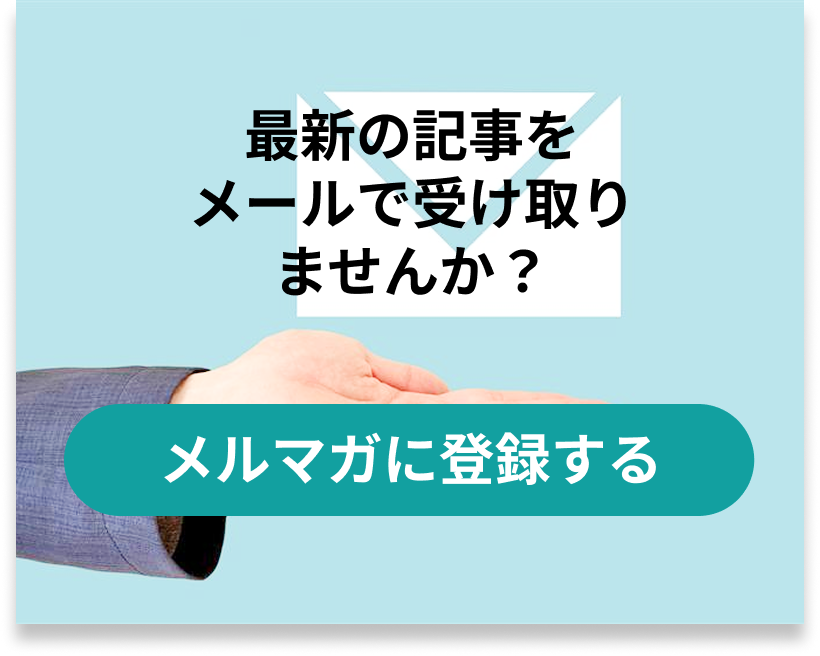view 3205
フリーのコンサルタントが加入すべき社会保険とは?|独立前に知っておきたいおカネの話
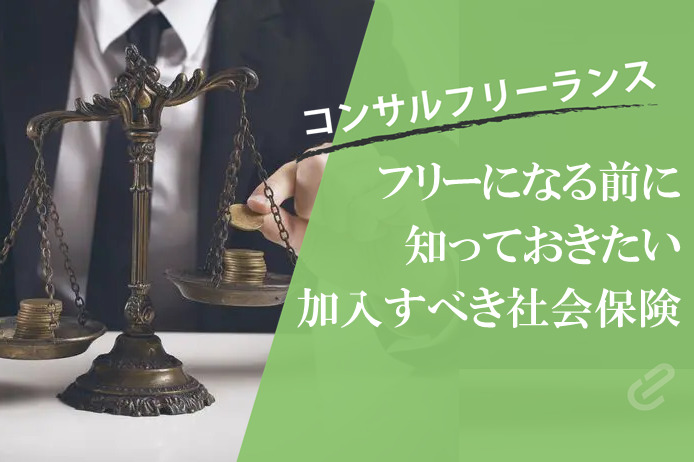
フリーコンサルの税金・社会保険・手取りについて。今回は社会保険について言及
コンサルファームに所属するコンサルタントは、社会保険への加入が義務付けられており、税金以外にも負担がある一方で、健康保険や年金などの制度によって手厚く守られています。では、フリーランスになるとこれらの仕組みはどう変わるのでしょうか?本記事では、独立を考えるコンサルタントが知っておくべき社会保険制度の全体像を、分かりやすく解説します。
※フリーランスのおカネの話は全三部構成となっており、本記事は社会保険編です。
V1 税金の話
V2 社会保険の話 ← 本記事
V3 手取りの話
目次
サラリーマンは社会保険加入、フリーランスは国民保険加入
会社では、代表者や役員を含め皆が社会保険へ加入する義務があります。そのため、会社員は社会保険(社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の基本5つで構成されます)に加入します。(雇用保険・労災保険は、経営者は入れないといった制約があります)
これら5つの保険は、保険料の約半分を会社が払い、約半分が社員の給料から天引きされております。(労災保険のみ全額会社負担)
フリーランスのコンサルが加入する国民保険
一方、フリーランスには国民保険への加入義務があります。入らないと保険証もゲットできません。(国民保険は、国民健康保険、国民年金保険、介護保険の3つで構成されます)
雇用保険や労災保険には加入出来ませんので、その分保険料は払わなくて済みますが、育児休業や傷病休暇等を取ったとしても手当を貰うこともできません。また、社会保険は会社と社員が保険料を折半していますが、国民保険は全額自己負担です。
特に、会社員とフリーランスの差が出るのが、年金面です。厚生年金は収入に応じて取られるので結構な金額になりますが、国民年金保険は収入に関係なく、定額(月16,980円(令和6年度))ですので安く済みます。
(↓下に続く↓)
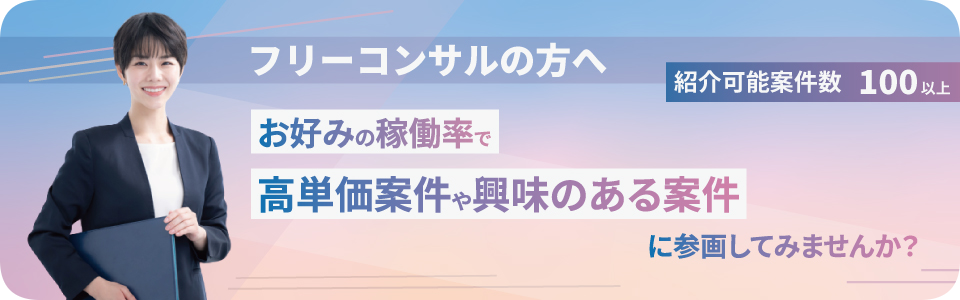
会社員とフリーコンサルの社会保険料の合計を比較してみた
税金の計算と同様に、35歳・扶養家族なし・東京都中央区在住という人物の2025年度の社会保険料を算出してみます。給与とコンサルフィーはイコールという前提です。
■ 年収(売上)800万円のケース(月額)
| コンサルファーム勤務 (社会保険加入) 本人負担分のみ | フリーコンサル (国民保険加入) | |
| 健康保険 | 約40万円 | 約64万円 |
| 年金保険 | 約71万円 | 約20万円 |
| 労災保険 | (会社負担) | (適応対象外) |
| 雇用保険 | 約4万円 | (適応対象外) |
| 介護保険 | (適応対象外) | (適応対象外) |
| 合計 | 約115万円 | 約84万円 |
■ 年収(売上)1,500万円のケース(月額)
| コンサルファーム勤務 (社会保険加入) 本人負担分のみ | フリーコンサル (国民保険加入) | |
| 健康保険 | 約75万円 | 約89万円 |
| 年金保険 | 約71万円 | 約20万円 |
| 労災保険 | (会社負担) | (適応対象外) |
| 雇用保険 | 約8万円 | (適応対象外) |
| 介護保険 | (適応対象外) | (適応対象外) |
| 合計 | 約154万円 | 約109万円 |
会社員のメリット
上記の比較からお分かりの通り、いずれの年収においても、会社員の社会保険料の負担額が高くなりました。一番大きな差は年金保険額にあります。厚生年金保険(会社員)と国民年金保険(フリーランス)というところで分かれますが、厚生年金に対する積立額が大きいということです。なので、会社員は支払う年金額が多い分、定年で年金受給となった場合、受給額が国民年金保険とは雲泥の差です。(ただ、少子高齢化により年金の支給が担保されるかという保証はありませんが)
他、雇用保険に加入ができ、有事の際の保障が受けられるというメリットも前述の通りです。デメリットはこれらメリットの逆ですね。
なお、上記の比較では独身の場合を想定しておりましたが、結婚して配偶者がいると年金保険の金額が異なる場合があります。例えば配偶者が年収130万円未満である場合、厚生年金保険(会社員)加入であれば配偶者は扶養に入り年金保険料の納付は必要ありません。一方、国民年金保険(フリーランス)には扶養の概念が無いため、配偶者分の国民年金保険料を納める必要があります。(配偶者分を負担すると考えた場合)このような場合、フリーランスと会社員の社会保険料負担差分は当然小さくなります。
フリーランスは公的な社会保障が手薄くなるため、節税も兼ねて自身で補完すると良いでしょう。いくつか例を挙げてみました。
◆iDeCo(個人型確定拠出年金)
・掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税を軽減できる
・原則60歳まで引き出せないため、流動性が必要な場合には他の積立手段を検討しても良い
◆国民年金基金
・iDeCoと併用可能。掛金は全額所得控除の対象となり、将来の年金額を増やせる
・掛金は年齢に応じて増加するため、早めに加入する方が効率的
・ただし、途中解約はできない
◆所得補償保険
・税務上、業務関連の保険料は必要経費として計上可能
・万一働けなくなった場合に備えるため、月額収入の50~70%をカバーするプランがおすすめ
◆小規模企業共済
・月額7万円までの掛金が控除対象で、節税効果を得つつ将来資金を確保できる
・退職金や事業閉鎖時の資金として利用可能
・途中解約した場合は掛金総額よりも受取額が少なくなることも
◆その他(医療保険・生命保険)
・医療保険特約で予期せぬ医療費に対応
・生命保険料控除を活用することで節税を最大化
まとめると、
フリーランスは、自由に働けて社会保険料負担が少ない反面、会社に所属することで得られる手厚い社会保険の恩恵を受けられません。また、ご家族の有無、配偶者の仕事なども含め、長いスパンで考えた際、どちらが良いのか、社会保険という観点でも比較検討する必要があると言えます。
なお、税金等なども考慮すると手取りの金額は異なってきます。「税金」「手取り(近日公開)」に関してまとめた記事もご確認ください。
💡フリーコンサルの社会保険のポイントを理解したところで…
フリーランスとして安定した収入を得るためには、実際の案件獲得が重要です。効率よくコンサル案件を見つけたい方は、案件紹介サイト「コンサルパートナーズ」 をぜひご活用ください🔎
[v045]
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社
- 事業会社にて企画管理関連のキャリアを積んだ後、コダワリに中途入社。チームのためなら何でもこなす、営業部の汗っかき。プライベートでは音楽と猫を愛するインドア人間。
最新の投稿
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社
- 事業会社にて企画管理関連のキャリアを積んだ後、コダワリに中途入社。チームのためなら何でもこなす、営業部の汗っかき。プライベートでは音楽と猫を愛するインドア人間。